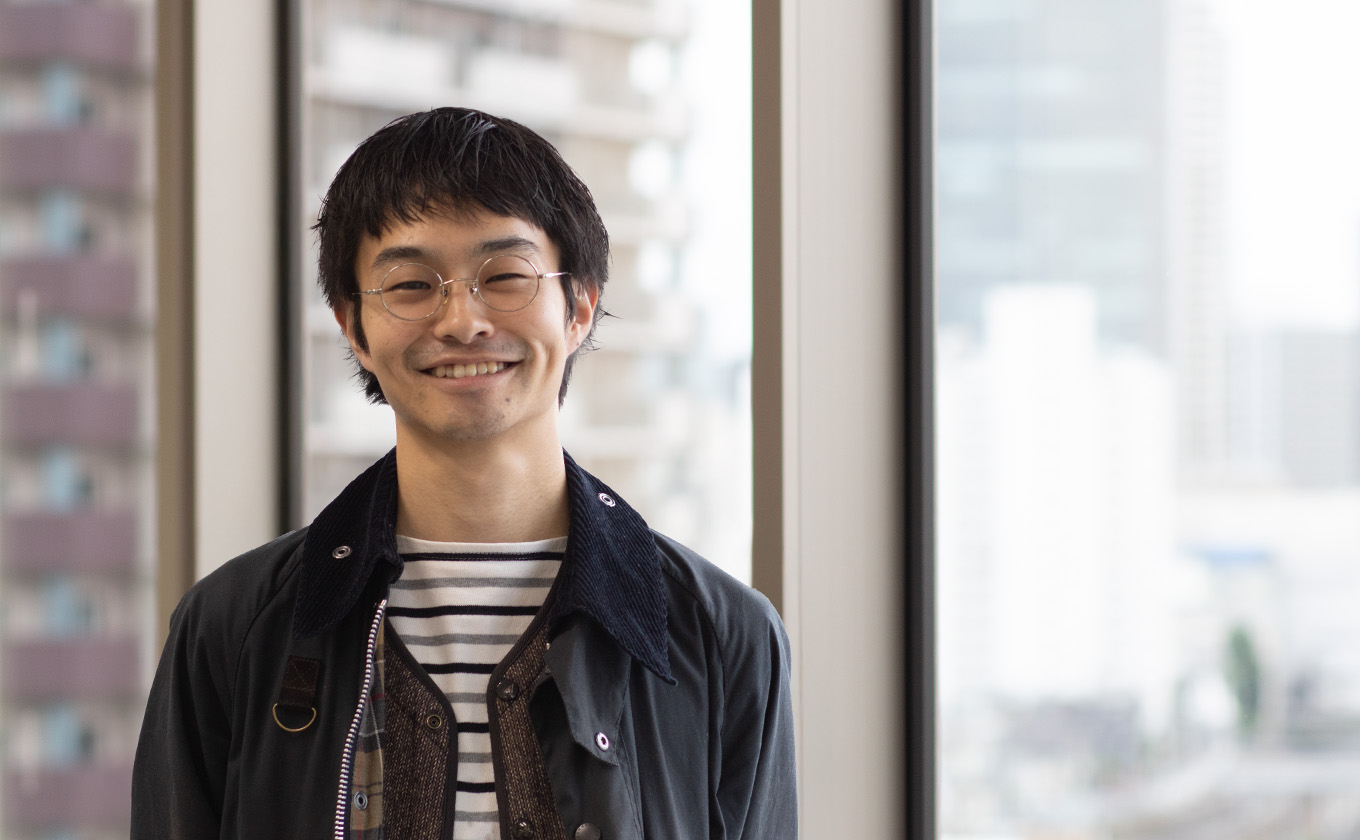英国の広告代理店からインハウスPdMへのピボット。企画~機能実装をデイリーで実現するPJ進行に必要な“意志”とは
-

キタムラ
キタムラ
慶応義塾大学卒。広告代理店でWebディレクターとして海外ブランドのECサイト運用に携わった後、代理店業務の板挟み状態からの脱却を求めクーリエへジョイン。入社後はSQLやデータ分析スキルを獲得し、「みんなの介護」「みんなの介護求人」と事業を横断で複数プロジェクトの進行管理やカスタマージャーニー設計を推進する。PdMとしてプロジェクトの幅を広げることが目標。
裁量ある環境を求めた転職決断
前職ではどのような仕事をされていたのですか?
前職は、イギリスに本社を構えるECサイトビジネスの広告代理部門でした。Webディレクターとして所属していたのはマーケティング部門で、日本市場向けのECコンテンツを中心に、日々戦略と実行を繰り返す環境でした。
具体的には、日本のユーザーに響くキャンペーン設計や商品ページの訴求設計、コンテンツの企画・運用までを担当していました。売上データやアクセスログを分析しながら、コンテンツの出し方ひとつで反応が大きく変わる実感を得られたのは、この時期に得た貴重な経験です。
もともとマーケティングという分野に強い関心があったこと、またこのブランドがイギリス国内でも特に成功を収めていたEC企業だったかことから志望し、実績のある企業で、かつ現地の一流の現場でマーケティングを学びたい──そんな思いで入社を決意しました。
私には幼い頃から「世界のどこでも生きていける力を身につけたい」という想いがあり、文化も市場も異なる環境で、日本とイギリスの“あいだ”に立って成果を出すという経験は、自分のマーケティング思考を大きく鍛えてくれました。
なぜ転職しようと思ったのでしょうか?
前職で働くなかで、日々感じていたのは「どんなに小さなことでも、すべてクライアントの承認が必要になる」という構造的な制約でした。これは広告代理店業務の性質上、当然ともいえる前提なのですが、次第にそのテンポの遅さにフラストレーションが募るようになっていきました。
たとえば、ECサイト内のバナーの色味を少し調整したい、商品紹介ページの構成を改善したいといった、ごく小さな改修案ひとつを実現するにも、まず提案資料をまとめ、社内で承認を通し、クライアントに提案し、先方社内でも稟議が必要になる──。結果的に、たった1行のテキスト変更でも数週間を要することもあり、現場の感覚と意思決定のスピードが噛み合わないもどかしさを強く感じていました。
もちろん、それが代理店という立場における「慎重さ」や「信頼構築のプロセス」であることも理解はしていました。ただ一方で、「もっと早く手を動かして、検証して、改善につなげたい」という気持ちを抑えきれなくなっていたのも事実です。
自分のキャリアをどう築いていくかを改めて考えたとき、「承認を待つ立場」ではなく、「自ら考え、判断し、実行できる環境に身を置きたい」と強く思うようになりました。このまま同じリズムに身を置き続けるよりも、挑戦の幅を広げ、より主体的に動ける場所へ進むべきではないか──その確信が、転職を決めた最大の理由です。

クーリエを選んだ理由について教えてください
これまでの経験を通じて私は、「自社プロダクトを持ち、マーケティングをインハウスで推進している企業でこそ、真の価値ある施策を生み出せる」という確信を抱くようになりました。自社でユーザーデータを保有し、サービス成長に責任を持つ立場でなければ、本質的なマーケティングには携われない——そう強く感じていたからです。
そうした明確な軸を持って転職先を探す中で、クーリエはまさにその理想条件に合致していました。自社サービスを展開し、1stパーティデータを活かしてマーケティングを自社で完結させている。その点に最も強く惹かれました。
もうひとつの決め手は、自分の“興味の輪郭”がまだ完全に定まっていなかったことです。SEO、コンテンツ制作、オンライン広告運用など前職では限定的な経験が中心だったため、「自分はマーケティングのどの領域に最も適性があるのか」を見極めるためにも、幅広い業務にチャレンジできる環境を求めていました。そしてクーリエには、分野横断的に業務に関われるだけでなく、一人ひとりに任される裁量も大きく、自ら手を動かして成長できる仕組みがあることが、面接を通じてリアルに伝わってきました。
特に印象的だったのが、社員や役員との面談で感じた「施策実行までのスピード感」でした。社内での情報共有が徹底されていて、たとえばその場で出たアイデアが翌週にはプロトタイプとして形になっているという話も聞き、前職の慎重なプロセスとは対照的な“動きの速さ”に、強く惹かれました。
この環境であれば、自分自身のスキルアップも、ビジネスパーソンとしての成長も、これまでの何倍ものスピードで実現できる。そんな確信を抱き、私はクーリエへの入社を決意しました。
一気通貫の業務で磨かれるスキル
入社後はどんな業務に取り組んでいますか?
現在は、当社が展開する2つのWebサービス──「みんなの介護」と「みんなの介護求人」において、WebアプリケーションのUX改善を中心に担当しています。
具体的には、CVR(コンバージョン率)やユーザーの遷移・離脱データの分析から課題を抽出し、それに基づいた打ち手を検討。開発要件定義、エンジニアとの仕様すり合わせ、実装ディレクション、リリース後の効果検証に至るまで、ひとつの改善サイクルを一気通貫でリードしています。
中でも主軸として担っているのが、「ブランドページ」の価値向上プロジェクトです。ブランドページというのは、昨年8月にリリースした「各法人が保有するブランドから施設を探せる」機能のことです。

従来は施設単位での検索が基本だったため、ユーザーが複数のページを行き来しなければならず、比較検討のハードルが高くなっていました。これを改善し、同一ブランド内の複数施設の傾向や価格帯を一覧で確認できるUXを実現しました。
ユーザーにとっては意思決定がよりスムーズになり、施設への愛着(ブランドアタッチメント)を高める導線にしました。クライアントにとっても、掲載価値を可視化しやすくなるため、契約継続率の維持・向上に直接つながる設計になっています。
このような事業・UX・データを結びつける経験の中で、私自身のスキルもハード・ソフト両面で確実に進化していると感じています。
まずハードスキルの面では、ユーザーログの抽出・分析に必要なSQLスキルが大きく伸びました。仮説に基づいて必要なデータを設計し、適切な粒度と時間軸で抽出することで、定量的な裏付けを持って改善案を立てられるようになっています。
また、Microsoft Clarityなどのヒートマップツールを活用し、クリック位置やスクロール深度といった視覚的な行動データを読み解く力も磨かれました。これにより、「なぜこの導線で離脱するのか」といったユーザー視点での課題発見がより立体的になったと実感しています。
さらに、分析したデータをスプレッドシート上で多次元的に整理し、カテゴリ別・導線別に比較分析できるスキルも身につきました。BIツールのように扱うことで、施策のインパクトを即座に可視化し、意思決定スピードを高める工夫も重ねています。加えて、抽出したインサイトを開発チームに正しく伝えるための要件定義力や、UX改善の要素を構造化して仕様書へ落とし込む力も、実務を通して着実に鍛えられてきました。
一方でソフトスキルの面では、複数のプロジェクトを同時に走らせる中で、タスクの優先順位を柔軟に調整しながらスケジュール管理を行うマルチタスク能力が大きく伸びたと感じています。特に開発、CS、営業といった多様な部門と連携しながら、ロジ面のすり合わせや実行スケジュールの合意形成を行う中で、全体を俯瞰しながら物事を進める視点が自然と養われました。
また、施策をただ「やるかやらないか」で判断するのではなく、それがどれだけ事業に貢献しうるかという観点から優先順位をつける視座──「事業貢献度に基づく判断軸」も体得できたと実感しています。
キタムラさんにとって、この仕事のやりがいは何ですか?
インハウスのPdMとして働くなかで、最大のやりがいを感じるのは、自分が立てた施策やアイデアがダイレクトにサービスへ反映され、その結果をデータとしてすぐに確認できる点です。数字としての成果がリアルタイムで返ってくるため、施策が「刺さった」ときの手応えは非常に大きいですし、仮にうまくいかなかった場合でも、そこから何を学ぶか、どう改善するかをすぐに次に活かせる環境があります。
代理店時代と比べて、こうした意思決定から実装までのスピード感には本当に驚かされました。印象的だったのは、あるとき正午に決まったデザイン修正が、その日の18時にはすでに本番環境に反映されていたこと。細かな変更であっても、改善余地があると判断すれば即アクションに移せるこのスピード感は、まさにインハウスならではの醍醐味だと感じました。
高速でPDCAを回しながら、データを根拠にしつつ仮説検証を積み重ねていく。そうした日々の積み重ねがプロダクトの成長にも直結し、それがそのまま自分自身の成長にも返ってくる──。この循環があるからこそ、「今、本当に手応えのある仕事ができている」と実感できています。
徹底した価値創出へのこだわり
今後のキャリアビジョンについて教えてください
いま私が掲げている目標は、プロダクトマネージャー(PdM)としての“守備範囲”を拡張していくことです。これまでは既存プロダクトのUI改善や導線調整といった「改善型」のタスクを中心に担ってきましたが、今後は“ゼロから立ち上げる”タイプの仕事──新規機能や新ページの設計・実装ディレクションにも積極的に関わっていきたいと考えています。
そのためには、UXや画面設計だけでなく、インフラ寄りの理解も不可欠です。特に、サービスの稼働状況やシステム負荷を示すメトリクス(例:APM、レスポンスタイム、エラー率など)の基礎的な概念や、それらをどう取得し可視化するかといった「データ取得環境」についての知識は、今まさに学習・実践を重ねている領域です。
クーリエは、年次や職種に関わらず、プロジェクトの企画段階からリリース・効果検証まで一貫して携われる環境があるのが大きな特徴です。だからこそ、自ら機会を掴めばどんなフェーズにも挑戦できます。今後は、より多様なプロジェクトに関与する中で、PMBOKなど体系的なプロジェクトマネジメント知識にも裏付けられた「再現性ある推進力」を身につけていきたいと考えています。
実際、クーリエでは複数のプロジェクトが常に並走しており、タスクの優先順位は週単位、日単位で変わっていくこともあります。そうした中で、PdMとしてタスクの進捗状況を正しく捉え、ステークホルダーの期待値を調整しながら、限られたリソースを最適に配分できるように努めていきたいと思います。

クーリエの理念10valuesの中で特に大切にしていることを教えてください。
最も大切にしているのが、「ファクトとインサイトからの価値創造」という考え方です。特にPMF(Product Market Fit)を目指すフェーズにおいては、この2つのバランスが欠かせないと強く感じています。
“自分がカスタマーだったらどう思うか”という視点からの仮説立ては確かに重要です。共感や直感から生まれる発想には、言語化しきれないリアルなインサイトが宿ることもあるからです。しかしその一方で、主観に頼りすぎると、実際のユーザー行動とはズレたUIや導線をつくってしまうリスクもあります。
逆に、ファクト──たとえば数値データや行動ログ、ヒートマップといった観測可能な情報だけを軸に意思決定しようとすると、今そこにない“潜在的なニーズ”や“可能性のあるユースケース”を見落としてしまう可能性がある。ファクトは過去の結果であり、未来の兆しをすくい取るにはインサイトという補助線が必要だと感じています。
だからこそ、日々の分析・設計・提案の場面で「この施策はユーザーにどんな行動を起こしてほしいのか?」という問いを軸に置くようにしています。そのうえで、ログやメトリクスといった“動かぬ事実”と、ユーザーインタビューやUI観察から得られる“人の気配”の両方を丁寧に読み解き、判断とアウトプットを構築しています。
ファクトが導く根拠と、インサイトがもたらす可能性。この両輪が揃ってはじめて、PMFを推進するプロダクトに深みが生まれると信じています。
最後に、プロダクトマネージャーを志望する方に向けてメッセージをお願いします
クーリエは、仕事にひたむきに向き合えば必ず成長できる環境です。今まさに組織が急成長フェーズにあり、挑戦の連続。手を動かすほどに、自分の変化を実感できる会社だと思います。
中でも活躍している人に共通するのは、「自走力」と「切り替えの早さ」です。
自走できる人とは、指示を待つのではなく、状況を自分で整理し、何をすべきかを考えたうえで、必要な承認を得て素早く実行に移せる人。プロジェクトを前に進めるために何が必要かを常に意識している姿勢が、信頼にも成果にもつながります。
一方、切り替えの早い人というのは、うまくいかないことや想定外の出来事に直面したときに、「じゃあ次はどう動く?」と前を向いて思考を切り替えられる人。感情に引っ張られずに建設的に行動できるかどうかが、長く活躍するうえで重要だと感じます。
まだ自分の得意分野や興味が定まっていない方でも、クーリエには多様な業務に関わりながら、ビジネスパーソンとしての土台を築けるチャンスがあります。
面接でも、キャリアの方向性や小さな疑問に対して丁寧に向き合ってもらえるので、少しでも気になる方は、ぜひ一度チャレンジしてみてください。きっと、自分の可能性を広げられる場所だと思います。